現代の連絡は「送ればすぐ届く」が当たり前ですが、当時はまったく逆です。届くまでの時間も、お金の感覚も、そして連絡手段の選び方も違います。
この記事では、(1)国内と国際の配達日数の目安、(2)郵便局という国の仕組み、(3)電報という“急ぎの連絡”の位置づけ、(4)料金を当時と現在価値(目安)で――をまとめて、ばけばけの文通シーンが想像しやすくなる形に整理します。
まず結論|明治23年(1890年)の国際郵便は「数週間〜1か月以上」
明治23年(1890年)の国際郵便は基本的に船便です。航空便はなく、海上輸送が前提でした。
そのため、海外へ手紙を出した場合の所要日数は、ざっくり言うと数週間〜1か月以上。相手から返事が返ってくるまで(往復)で考えると、2〜3か月が普通の感覚になります。
ばけばけの文通シーンが「間が長い」「返事が来ない時間が長い」と感じるのは、演出というより、当時の通信の現実に沿っています。
現在価値の換算ルール|当時の金額だけだと体感しにくい
金額は体感しやすいように、この記事では明治の1円 ≒ 現在3万円(目安)で統一して換算します。したがって1銭 ≒ 約300円の感覚です。
もちろん、現在価値の換算は「何を基準にするか」(賃金・米価・物価など)でブレます。この記事ではブレを広げず、読者が途中で迷子にならないように、あえて基準を1つに固定しています。
明治23年(1890年)に“郵便局”はすでに日常だった
郵便制度は明治4年(1871年)に官営として始まり、明治期に全国へ広がっていきます。つまり明治23年(1890年)は「郵便があるかどうか」の時代ではなく、郵便がある前提で生活や仕事が回っている時代です。
江戸時代の飛脚(民間の仕組み)に比べて、郵便局は“国の仕組み”として整えられます。誰が運んで、どこを経由して、どう届けるかが制度として整い、住所・料金・配達のルールが揃っていく。そこが大きな違いです。
国内の手紙は何日?|「数日」で届く時代
国内郵便は、主要な地域間であれば数日程度で届くのが基本でした(地域や交通事情で前後)。
この「数日」という感覚は、今でいう宅配の感覚に近いものがあります。もちろん現代ほどの正確さはないとしても、相手に「来週には届くはず」と見込みを立てられる。それだけで、人の動きや商売の回り方が変わっていきます。
国内郵便が生活に入り込むと、何が変わる?
- 「返事が来る時期」が読めるので、約束や予定が立てやすい
- 商売や採用、役所の連絡が“待ち時間込み”で計画できる
- 家族の用事(冠婚葬祭など)の段取りが組みやすくなる
国際郵便は何日?|船便で“待つ”ことが前提
国際郵便は船便なので、距離・寄港地・天候の影響を受けます。目安として、
| 区分 | 日数の目安 | イメージ |
|---|---|---|
| 国内(主要地域間) | 数日 | 「来週には届く」程度の見込み |
| 日本 → ヨーロッパ方面 | 30〜45日 | 「来月の後半に届くかも」 |
| 日本 → 北米西海岸方面 | 20〜30日 | 「うまくいけば来月」 |
| 往復(返事が届くまで) | 2〜3か月 | 季節が変わる頃に返事が来る |
この時間差があるので、国際文通は「情報のやり取り」というより、気持ちや状況を“時間ごと預けて”交換する行為になります。ばけばけの文通がしみじみと見えるのは、この時間感覚が背景にあるからです。
料金はいくら?|当時と現在価値(目安)で見る
国内郵便(明治23年/1890年)の目安
- はがき:1銭(現在価値の目安:約300円)
- 封書:2銭(現在価値の目安:約600円)
この価格帯だと、手紙は「特別な贅沢」ではなく、日常の連絡として使える範囲に入ってきます。だからこそ、国内の手紙文化が広がっていきます。
国際郵便(宛先・重量で変動)
国際郵便は宛先(どの国か)や重さで料金が変わります。ここで大事なのは“きっちり何銭”よりも、国内より明確に負担が増えるという感覚です。
例として、外信はがきが3銭〜6銭程度の水準になる場合、現在価値の目安では約900円〜約1,800円ほどになります(目安)。
国内はがき(約300円相当)と比べると、海外へ出す手紙は「気軽」よりも「覚悟」を伴う行為に寄っていきます。
電報(電信)は何が違う?|“急ぎの短文連絡”の切り札
手紙とは別に、電報(電信)も使われていました。電報は、文章を長く書くためのものではなく、短文で要点だけを伝えるための手段です。
そして多くの場合、手紙より高くなりやすい。だから電報は「普段の会話」ではなく、「急ぎの用件」に寄っていきます。
電報の料金感(目安)
例えば国内電報が25銭前後の水準だとすると、現在価値の目安では約7,500円ほど。はがき(約300円)や封書(約600円)と比べると、使いどころが限られるのも納得できます。
電報が“短い言葉”になる理由
- 文字数(または語数)に制限がある
- 料金体系が分量に影響しやすい
- 「急ぎの用件」目的なので、要点だけに絞る
当時の電報文が素っ気なく見えるのは、気持ちが冷たいのではなく、仕組みと料金がそうさせる面があります。
郵便局と電信は同じ建物?|「一緒の局舎」もあれば別の場合も
都市部では「郵便」と「電信」を同じ局舎で扱う例(郵便電信局など)があります。地方でも近接して運用されることが多かった一方で、どの町も必ず同じ建物、と言い切るのは避けたほうが安全です。
ばけばけの世界に当てはめるなら、「普段は手紙、急ぎは電報」という使い分けを想像すると、当時の通信事情が自然に腑に落ちます。
届くまでのリスク|遅延・紛失・検閲の可能性
国の制度が整っていても、現代ほど安定はしていません。とくに国際郵便は船便なので、天候や寄港の事情で遅れることがあります。破損や紛失のリスクも、現代より高かったと考えるのが自然です。
検閲については、「常に検閲されていた」と断定はできません。ただ、治安や外交上の事情によって郵便物が問題視され、差し止めや取り締まりの対象になりうる可能性は残ります。
郵便配達員の仕事|「届く」は人が支えていた
郵便が届くのは制度だけではありません。郵便局で仕分けし、担当区域を巡回し、届ける。その一連の仕事があって、手紙は相手の手元に届きます。
徒歩での配達が基本だった時代、雨の日も風の日も歩いて届けるのは重労働です。遠い国から届く手紙が特別に感じられるのは、距離や時間だけでなく、そうした労力が背景にあったからでもあります。
まとめ|明治23年(1890年)の国際文通は「時間を預ける通信」
- 国内郵便:数日で届くのが基本
- 国際郵便:船便で数週間〜1か月以上(往復で2〜3か月)
- 国内料金の目安:はがき1銭(約300円)/封書2銭(約600円)
- 国際郵便は国内より負担が増えやすい(例:3〜6銭=約900〜1,800円の感覚)
- 電報は高額で、急ぎの短文連絡に寄る(例:25銭前後=約7,500円の感覚)
ばけばけの国際文通は、現代の連絡手段とは別物です。届くまでの時間、支払う費用、そして待つ覚悟。その前提を知った上で文通シーンを見ると、一通の手紙の重みが変わって見えてきます。
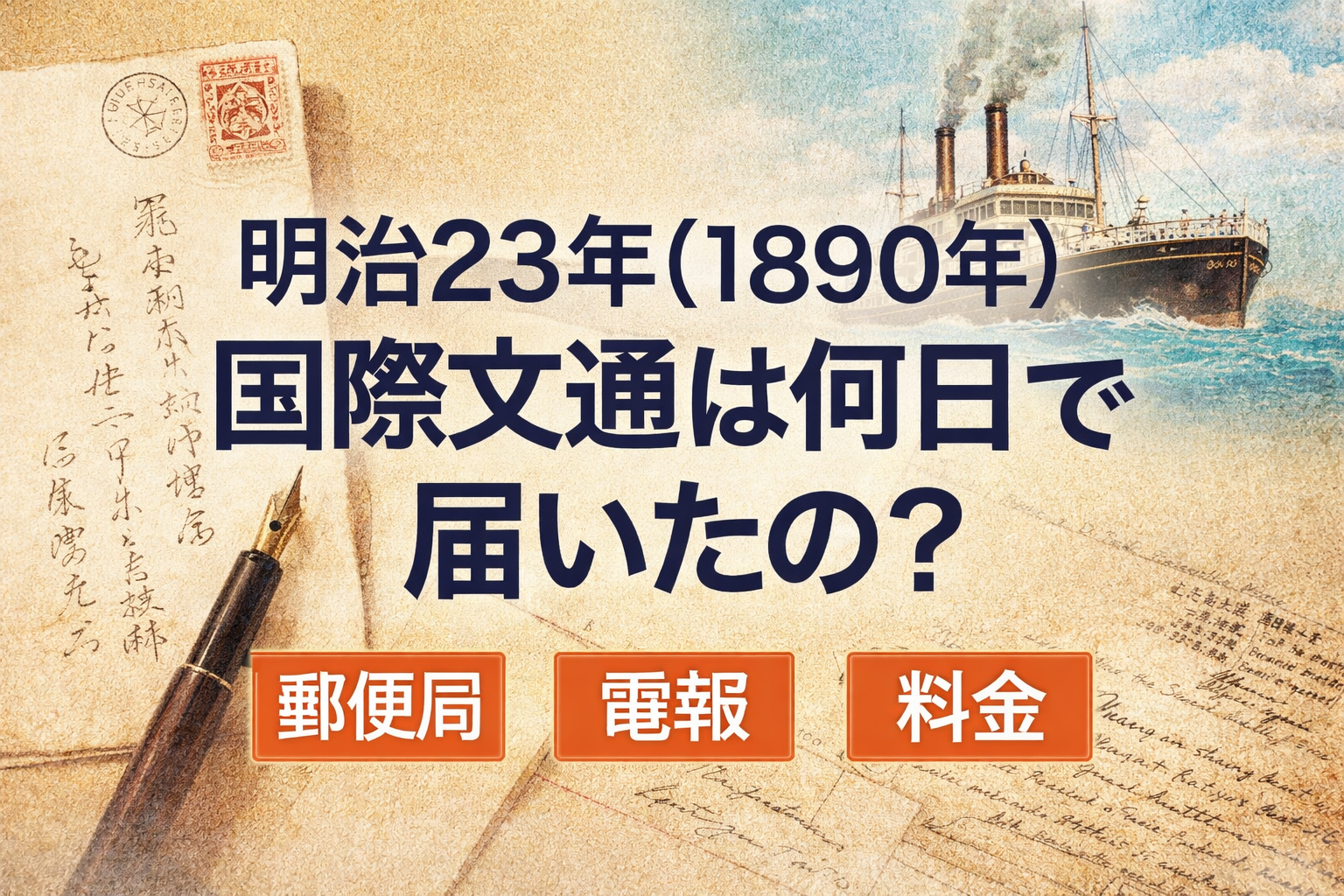


コメント